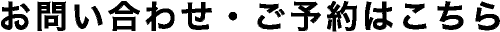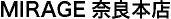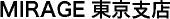年々進化する車両盗難の手口により、従来型の防犯対策だけでは愛車を完全に守るのが難しくなってきています。実際、車の盗難被害は2023年は認知されているだけでも5,762件と公表されています。
本記事では、これまでに2万台を超える車両に防犯システムを導入してきたカーセキュリティ専門店の店主が、2025年時点での盗難テクニックや対処法、実際の対策事例を交えて、最も車が盗難されにくい最強の対策を解説いたします。
また、当店では防犯カスタムの施工や、セキュリティに関する個別相談も承っております。奈良本店および東京支店にて対応可能ですので、メールやお電話にてお気軽にお問い合わせください。
Contents
自宅で車の盗難防止対策が必要な理由
まず、そもそも盗難対策は本当に必要なの?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、朝起きたら自宅の駐車場から愛車が消えていた、なんてことが現代社会では平然と起こってしまいます。
車の盗難被害はなくならない
平成15年(2003年)をピークに、自動車盗難の認知件数は年々減少しています。警察庁の統計によれば、当時は年間6万件を超える盗難が発生していましたが、近年では1万件ほど以下にまで落ち込んでいます。
しかし、これは「盗難がなくなった」のではなく「手口が巧妙化して発見が難しくなった」「一部の高級車にターゲットが集中している」といった構造変化を意味します。
実際、盗まれる車両はトヨタ・レクサス・ランドクルーザー、アルファードやハイエースなど一部の車種に集中しており、短時間で海外に転売・密輸されるルートも確立され、高値で売買が行われています。
そのため、盗難の被害をゼロにすることは極めて難しく、自分で対策を立てる必要があります。
メーカー純正のセキュリティシステムでは防げない
メーカー側も純正セキュリティを装備して防犯を試みていますが、純正のセキュリティではプロの窃盗団から車を守ることはできません。その理由はセキュリティが共通化されているためです。
車種ごとのセキュリティ構造は同じのため、一度仕組みが解明されると、その手口が同車種にもそのまま通用してしまいます。
犯行グループは新型車の構造やシステムを常に研究しており、ひとつの車両で攻略に成功すれば、その情報はすぐに仲間内で共有されます。結果として、同型の車種が次々と狙われる連鎖が起こるのです。
実際、現在確認されている盗難手法は、すでに完成された手口として流通しており、全国的に同様の被害が多数報告されています。
純正セキュリティは車両個別のカスタマイズがほとんどなく(生産ラインで工程が決まっているため個別カスタマイズがそもそもできない)、標準化された防御=狙いやすいセキュリティになっているのが現実です。
そして、盗難が実行されるまでの時間もわずか。純正のセキュリティアラームはあっさりと無力化され、数分以内に車両が無音で持ち去られるケースがほとんどです。
2025年の盗難の手口種類
では2025年現在、窃盗団はどんな盗難手口で車を盗んでいくのでしょうか。ここでは主に代表的な盗難手口をご紹介します。
リレーアタック
リレーアタックは、スマートキーが発するわずかな電波を特殊な装置で受信・増幅し、それを車両へ中継することで、車に「正規のキーが近くにある」と思い込ませてしまう手法です。
通常、スマートキーは車両の近くにあるときだけ反応するように設計されており、距離がある状態では車がキーを認識しないようになっています。しかし、この仕組みには盲点があります。
犯人は、住宅の玄関や窓際などに置かれたキーから漏れている微弱な電波をキャッチし、それを強化して車へ送信するのです。車側はそれを正規のキー信号だと誤認し、自動的にドアロックを解除し、エンジンの始動も可能にしてしまいます。
この手口は特に、自宅の玄関近くにスマートキーを保管しているケースで発生しやすくなります。キーが外部から近い位置にあることで、犯人が信号を拾いやすくなるからです。
また、車が道路に面した場所に駐車されている場合は、窃盗団が車両に近づきやすいため、リレーアタックを実行するハードルがさらに下がります。
スマートキーの利便性は高い一方で、このようなセキュリティリスクを抱えていることを認識し、キーの保管場所や駐車環境の見直しが求められます。
CANインベーダー
CANインベーダーは、自動車内部の通信システム「CAN(Controller Area Network)バス」の脆弱性を突く、新たな自動車盗難の手法として近年注目されています。
現代の車両は、エンジンやドアロック、各種電子装置がCANバスを通じて常時データをやり取りしており、効率的な制御が可能になっています。しかし、その利便性の裏に、外部から不正アクセスされやすいというリスクが潜んでいるのです。
犯人たちは専用ツールを用い、車体の一部に物理的な接触を行いながら、CANバスに偽装信号を送信します。これにより、本来スマートキーが必要な操作であるドアの解錠やエンジンの始動を、鍵なしで実行できてしまうのです。要するに、車の制御を不正に奪うことが可能になるというわけです。
さらに、この侵入方法は一見して外部からは分かりづらく、短時間で完了するケースが多いのが厄介です。窓を割る、鍵を壊すといった目立つ破壊行為が伴わないため、盗難後に痕跡が残らず、発覚が遅れる可能性もあります。
このような巧妙な手口に対抗すべく、自動車メーカーはソフトウェアのアップデートやシステム面の防御強化を進めていますが、いたちごっこの様相を呈しており、抜本的な対策には至っていません。
ゲームボーイ(キーエミュレーター)
見た目は無害でおもちゃのようにも見える「ゲームボーイ」と呼ばれる機器。実はこれ、極めて巧妙なキーエミュレーターであり、車両のセキュリティを無力化する危険なツールです。
この装置の機能は、スマートキーから発せられる無線信号を不正に読み取り、それをそっくりそのまま複製して再送信するというもの。外見上はただの携帯機器でも、実際には正規のキーと同じように振る舞い、ドアを開けたりエンジンを始動したりできてしまいます。
特筆すべきはこの手口が、リレーアタックやCANインベーダーのように信号を横取りして中継するのではなく、「本物そっくりのデジタルなスペアキー」を作り上げる点にあります。車側はその偽の信号を本物と区別できず、何の警告も出さずに受け入れてしまうのです。
本来、スマートキーの識別情報は正規ディーラーなど限られた機関しか扱えないよう設計されています。しかし、犯罪グループは特殊な装置と高度なノウハウを使い、車両から微弱な電波を傍受・解析して、鍵の情報をまるごと再現してしまうのです。
さらに近年では、こうした機器が海外の通販サイトなどで簡単に購入できるようになっており、そのリスクは以前より格段に高まっています。防犯対策を怠れば、車はあっという間に無防備な状態になります。
車の盗難防止に効果のないグッズ
インターネット上で紹介されている物理的なロックや対処法など、プロの窃盗団からすると盗難の抑止力としてほとんど効果がありません。以下のような効果のない防犯グッズを取り付けることで、逆に窃盗団に狙われるリスクが高まるケースもありますのでご注意ください。
ハンドルロック
ハンドルに装着して物理的に操作を封じるタイプのロック装置は、一見すると心強い防犯対策に見えます。しかし現実には、犯行現場でこうした装置があっさり突破される事例も珍しくありません。
窃盗犯はノコギリや電動工具を使ってハンドル自体を切断し、わずか数十秒でロックを無効化してしまうケースが報告されています。
この種の防犯器具は、それ単体では十分な抑止力にならないことも多く、「つけているから安心」と油断するのは危険です。
タイヤロック
タイヤに取り付けて車の移動を物理的に妨げるこのタイプのロックも、一部では防犯グッズとして人気があります。ですが、相手がプロの窃盗団であれば、その効果はほとんど期待できません。
実際には、強引に車両ごと動かして破壊されたり、専用工具であっという間に分解されたりと、簡単に無力化されてしまう例が多く見られます。
電波遮断ケース
スマートキーの電波を遮断してリレーアタックを防ぐために使われる専用ケースは、一定の効果が期待できる防犯アイテムとして知られています。しかしながら、これだけで完全に守れるわけではありません。
先ほど紹介したCANインベーダーや、ゲームボーイ(キーエミュレーター)のような、より巧妙な手法に対しては無力です。電波を遮っても、車両そのものに直接アクセスするタイプの犯行には歯が立ちません。
「ケースを使っているから安心」と油断してしまうことこそ、セキュリティの大きな落とし穴になる可能性があります。
車両カバー
車全体を覆うボディカバーは、一見すると車両の目立ちやすさを抑え、盗難の抑止につながりそうに思えます。しかし、実際には逆効果になるリスクもあります。
カバーによって視界が遮られることで、犯行中の様子が周囲から見えにくくなり、かえって盗難犯にとって都合の良い“隠れ場所”を提供してしまう可能性があるのです。
盗難防止ステッカー
「防犯装置作動中」「GPS搭載車」などと書かれたステッカーは、注意喚起の役割を果たすかのように思いますが、実際のところセキュリティ機器が装備されていない場合、犯人にとってはハッタリだとすぐに見抜かれ、抑止効果はほぼゼロです。
特にGPS装備車両の場合、装備していることを知らしめると社内の破壊活動に至るケースもございますのでNGです。
最強の盗難対策
では、車を盗難から守る最強の盗難対策とはどのようなものでしょうか。
結論からお伝えすると愛車の盗難リスクを限りなくゼロにするには「見せない」「触らせない」「エンジンをかけさせない」という3つの軸で対策を講じることが、最も堅実で確実な選択肢と言えるでしょう。
大切な愛車を守るため、実用性の高い防犯対策を具体的に紹介します。
車庫に入れて鍵をかける
車両盗難を防ぐ上で、最も効果を発揮するのが「車をそもそも見せない」という考え方です。窃盗犯は目に入った車を候補として選ぶ傾向があるため、通行人の視界にさらされた状態で駐車していると、どうしても狙われやすくなります。
その点、建物の裏側や屋内のガレージ、シャッター付きの駐車スペースなど、視界から遮断された場所に車を保管することで、そもそもターゲットとして認識されにくくなるのです。特にレクサスのように人気の高い車種であれば、通行人や不審者の目に触れない環境を意識することが重要です。
さらに、防犯的な視点で考えると、車両の存在を確認するために近づかなければならない環境は、それ自体がリスク要因になります。窃盗団はできるだけ短時間かつ無音で犯行を終えたいと考えているため、接近に手間がかかるだけでもターゲットから外される可能性が高まります。
加えて、物理的な施錠も見逃せません。たとえばガレージのシャッターや門扉に頑丈な鍵をかけておくことで、車両に物理的に接近するまでのハードルを上げることができます。つまり、ただの駐車ではなく「車体に触れることすら簡単にはできない状況」を作ることが、結果として非常に強力な防衛策となるのです。
もちろん、こうした屋内保管や厳重な施錠は、住環境や経済的な事情からすべての人にとって現実的とは限りません。しかし可能であるなら、これは非常に理にかなった対策です。単に「車を隠す」というシンプルな手段であっても、窃盗リスクを大幅に減らすことができます。
ダブルイモビライザー設備のセイキュリティシステムを完全に隠し込む
車のエンジンをかけるには、イグニッション回路とセルモーター回路の両方を制御しなければなりません。逆に言えばこの2系統をしっかりと制御できれば、車は動かせない仕組みになっています。
そこで高い評価を受けているのが、「クリフォード」や「パンテーラ」といったハイグレードなカーセキュリティシステムです。
これらにはダブルイモビライザーが搭載されており、エンジン始動に必要な2つの回路を同時に遮断します。単なる警報装置ではなく、物理的に車を動かせなくする防御力が魅力です。
とくにクリフォードは優秀で、仮に本体ユニットを取り外されたとしても、エンジン始動に必要な系統はシステム内部でロックされたままになります。バッテリーを抜かれても解除できず、車を動かすのは非常に困難です。
そして重要なのは、セキュリティ本体の取り付け位置。
プロの窃盗団は分解に慣れているため、見えやすい場所や配線が読みやすい位置にあると、発見されて回避されるリスクが高まります。だからこそ、犯人に見つけにくい場所に仕込むことが防犯成功のカギとなります。
もし窃盗団がクリフォードやパンテーラが装着された車を狙う場合、まずイモビライザーの場所を突き止め、完全に取り外し、さらに遮断された配線を元通りに復元しなければなりません。
そしてその作業を、警報が鳴り響く中で短時間でやり切る必要があるため、窃盗が現実的ではないのです。結果として、こうした車両はリスクが高すぎると判断され、犯人側も狙うのを避ける傾向があります。
一方、片方の回路しか止めない簡易的なシステムではプロ相手に歯が立たず、むしろ「手間のかからない車」としてターゲットになりやすいのが実情です。
本気で車両を守りたいなら、2系統を完全に遮断するダブルイモビライザー+隠密設置こそが、有効な選択肢と言えるでしょう。
なお、当店はクリフォードの正規取付代理店として累計20,000件以上のセキュリティ取付実績があります。奈良本店および東京支店にお気軽にご相談ください。
以下動画にてYouTubeチャンネル登録者40万人を超えている綾人サロン様に東京支店のセキュリティシステム取付についてインタビューしていただきました。ぜひご覧ください。
万が一、盗難されたときにやるべきこと
警察への通報と盗難届の提出
愛車がなくなっていると気づいたら、まず110番で警察に通報してください。現場確認のあと、盗難届を提出します。
手続きには車検証に記載されたナンバープレート番号や車台番号など、車両を特定する情報が必要です。届出が受理されると「受理番号」が発行されます。この番号は保険金請求や陸運局での一時抹消登録に必須なので、必ず控えて大切に保管しましょう。
保険会社への連絡
次に、加入している自動車保険会社へ連絡します。車両保険で「盗難」が補償対象になっていれば、契約金額を上限に保険金が支払われます。盗難事故の場合は免責(自己負担)がゼロ円に設定されているケースが大半です。手続き時には先ほどの盗難届受理番号が求められるので、すぐ伝えられるよう準備しておくとスムーズです。
ディーラーへの連絡
正規ディーラーにも速やかに連絡し、車載の追跡システム(位置追跡機能など)があればアクティブ化してもらいましょう。
窃盗団が通信モジュールを無効化している可能性はありますが、位置情報が残るケースもあります。あわせて鍵の無効化や車両登録の停止など、今後の手続きで必要なサポートを受けるためにも、早めの連絡が肝心です。
愛車を守るための最終チェック
ピークだった2003年と比べて認知件数は減ったものの、盗難の手口は年々ハイテク化し、依然として脅威は続いています。
純正セキュリティは共通仕様ゆえ解析されやすく、単体では突破されるリスクが高いのが現実です。ダブルイモビライザーの追加や屋内保管など、複数の防御策を重ねることで初めて“鉄壁”に近づきます。
万が一被害に遭った場合は、警察への通報と盗難届提出を最優先に、続いて保険会社への連絡、そしてディーラーでの追跡・無効化対応へと迅速に動くことで被害を最小限に抑えられます。
具体的な装備の提案から費用感の確認まで、どの段階でもお気軽にお問い合わせください。奈良本店および東京支店にて対応可能ですので、電話・メールでのご連絡をお待ちしております。